コラムCOLUMN
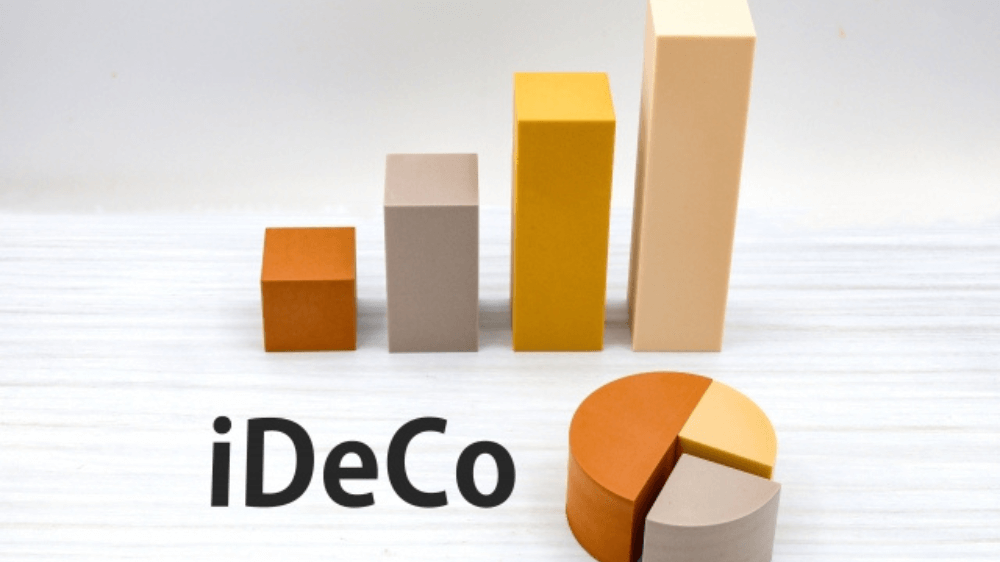
2024年12月、厚生労働省 社会保障審議会 企業年金・個人年金部会において、2年以上にわたる議論を経て、2025年のiDeCo(個人型確定拠出年金)の改正案が方向性として示されました。また、与党の令和7年度税制改正大綱には、確定拠出年金制度の大幅な見直しが盛り込まれています。
この改正は、「老後資産形成を国全体で後押しする」ことを目的としており、掛け金の引き上げや運用可能期間の延長など、多くの方に恩恵をもたらす内容となっています。ただし、現時点(記事公開日:2025年2月12日)では法案が成立しておらず、最終的な内容は今後の法令によって確定することに留意が必要です。
この記事では、2025年のiDeCo改正の概要と、その改正をどう活かすべきかについて詳しく解説していきます。
1. 2025年iDeCo改正の概要と注目ポイント

(1)掛け金上限の引き上げ
自営業者(第1号被保険者): これまで月額6.8万円(国民年金基金との合算)だった拠出限度額が、月額7.5万円に引き上げられる予定。
会社員(第2号被保険者): 企業年金の有無に関わらず、iDeCoの拠出限度額が見直されます。具体的には、企業型確定拠出年金(DC)の有無に関わらず、月額6.2万円まで拠出可能となる予定。
(2)70歳未満まで掛け金を拠出可能に
従来、iDeCoへの掛け金は65歳までとされていましたが、70歳未満まで拠出可能になることで、老後資産形成の幅が広がります。60代以降も働く方にとって、資産運用期間を延ばせるメリットが大きいです。
(3)企業型DCとの併用がしやすくなる
企業型確定拠出年金(企業型DC)の掛け金と合算で上限が拡大されることで、企業年金を活用している方でもiDeCoの利用が可能になるケースが増えます。
2. iDeCoの魅力と改正の意義
60歳まで積立を半強制的に継続
iDeCoの最大の特徴は、60歳まで積み立てた資金を引き出せない仕組みです。この制約は一見デメリットのように見えますが、実際には老後資金を確実に蓄えるための重要なメリットといえます。特に「貯蓄が苦手な人」「目先の支出を優先してしまう人」にとって、強制力のある制度は老後の安心を担保します。
2025年改正がもたらす意義
掛け金引き上げと拠出期間の延長は、個人が計画的に資産形成を行い、老後の経済的不安を軽減するための制度設計です。改正により、iDeCoを利用している人がさらに増え、「貯蓄から投資へ」という国の政策目標にも寄与するでしょう。
3. iDeCoが向いている人とライフステージ別活用法
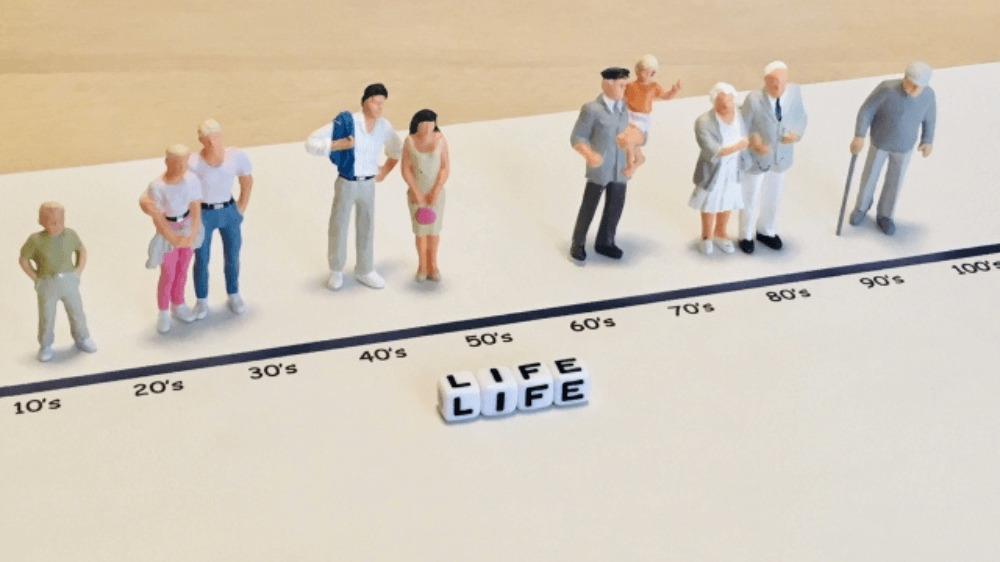
iDeCoは、以下のようなニーズを持つ方に特に向いています。
●老後資金を貯めたい人
●毎月強制的に貯蓄したい人
●税制優遇を受けたい人
●投資初心者で少額からスタートしたい人
ライフステージ別の活用法
60歳まで資金の引き出しが行えない為、年齢やライフステージに応じた運用を意識する必要があります。
●20代:リスクを取って積極運用を
若い世代は運用期間が長いため、少額からでもまずは投資で運用を経験し、知識を蓄えながら資産を形成しましょう。
●30代:収支の不安も定額積立で安定運用
結婚や住宅購入で支出が増える時期。少額でも積立を継続し、無理のない範囲で資産形成を続けることが大切です。
●40代:キャリアの安定期を活かす
収入が安定し始めるこの時期は、学資保険の代替としてiDeCoを利用するのも選択肢です。教育費や老後資金を計画的に蓄えましょう。
●50代:老後の具体的な計画を立てる
定年後の生活を見据えた安定運用が必要です。リスクを考慮して商品選定を行い、出口戦略を意識しましょう。
商品選びの基本
iDeCoの運用商品は、主に「元本確保型商品(定期預金など)」と「投資信託」に分かれます。リスク許容度や運用可能期間を考慮しながら、バランスの取れたポートフォリオを構築しましょう。
4. 注意点とリスク管理

60歳まで引き出せない制約
iDeCoの大きな特徴である「60歳まで引き出せない仕組み」は、長期的な老後資金を確保するための重要なメリットである一方、資金が急に必要になる場合には対応が難しいという側面があります。例えば、急な病気や介護費用、子どもの教育資金など、予期せぬ出費が発生した場合には、この制約が負担となる可能性があります。そのため、iDeCoを利用する際には、以下のような点に注意して計画を立てましょう。
1.手元資金とのバランスを意識する
iDeCo以外にも、流動性の高い貯蓄や短期的な資金管理を確保しておくことが重要です。預金やNISAなど、柔軟に引き出し可能な資産と組み合わせて、生活に必要な流動性を担保しましょう。
2.目標を明確にする
iDeCoは「老後資金の形成」に特化した制度であるため、運用資金の目的を明確にし、他の資金用途と分けて計画することが求められます。必要に応じて、家族と話し合い、将来のイベントや出費に備えた資金計画を作成しましょう。
受け取り時の税金に注意
iDeCoの受取時には、退職所得控除や公的年金等控除などの税制優遇を活用できますが、これには一定の計画が必要です。特に以下の2つの点に留意してください:
1.退職所得控除を最大限活用する計画を
一時金で受け取る場合、退職金と同じく退職所得控除が適用されます。ただし、退職金とiDeCoの一時金を同時に受け取ると、控除額が共有されてしまうため、必要に応じて受取時期を調整しましょう。例えば、退職金を受け取るタイミングを数年ずらすことで、その時の税制によりますが適切な控除を適用できるケースがあります。
2.公的年金等控除を活かした年金形式での受取り
iDeCoを年金形式で受け取る場合、公的年金等と合算して課税額が決定されます。公的年金等の受給額が高い場合には、iDeCoを年金形式で受け取ると課税負担が大きくなる可能性があります。受取期間や金額を工夫し、控除を最大限に活用する方法を検討しましょう。
これらの税制優遇を正しく理解し、計画的に活用することで、iDeCoのメリットを最大限引き出すことが可能です。
5. 弊社が提供するサポート
弊社は、iDeCoを含む資産形成における総合的なサポートを提供しています。特に、以下のようなポイントを強みにしています:
1.ライフステージに合わせた資金計画
iDeCoは個人のライフステージや収入状況、リスク許容度に大きく影響されます。例えば、20代であれば積極的な投資商品、50代であれば安定性を重視した商品を組み合わせることで、効率的な資産形成をサポートします。
2.出口戦略の立案
受取時の受取方法や時期を含む「出口戦略」を計画します。退職金や公的年金とのバランスを考慮し、負担を最小限に抑えた受取プランを提案します。
3.専門知識に基づいたアドバイス
iDeCoは専門性が高いため、自力での計画や運用に不安を感じる方も多い為、丁寧にサポートいたします。
6. まとめ:iDeCo改正を機に老後資金の準備を始めよう
2025年のiDeCo改正は、老後資金の形成を後押しする大きな制度改正です。掛け金上限の引き上げや拠出期間の延長といった改正内容をうまく活用すれば、将来の経済的不安を軽減することが可能です。
しかし、iDeCoは長期的な資産形成が求められる制度であるため、しっかりとした計画が必要です。手元資金とのバランス、受取時の税金対策、商品選定のポイントなどを理解し、自分に合った運用方法を選びましょう。
また、iDeCoを最大限に活用するためには、専門的な知識が求められる場面も多くあります。弊社では、個々の状況に合わせた運用プランや出口戦略の提案を通じて、お客様の資産形成をサポートいたします。
今すぐ始めることが将来の安心につながります。ぜひこの機会に老後資金の準備をスタートしてみてはいかがでしょうか?
【監修者情報】

[監修者名] (株)一期コンサルティング ファイナンシャルプランナー 船田勝太
[資格] AFP(日本FP協会認定)/2級ファイナンシャルプランニング技能士/公的保険アドバイザー/住宅ロ-ンアドバイザー
[経歴]
2014年~東京海上日動火災保険(株)
2017年~(株)一期コンサルティング
[専門分野] ライフプランニング/住宅資金相談/資産運用/保険相談
※ 注意
この記事は、一般的な情報を提供することを目的としており、特定の商品やサービスを推奨するものではありません。
個別の状況については、専門家にご相談ください。



